第50回 誠実な裏切り者
2014年は難病ALS(筋萎縮性側索硬化症)がクローズアップされた年でしたね。春にはALSを描いた三浦春馬さん主演のドラマ〔注1〕があり、夏にはアイスバケツ・チャレンジが話題になり、年末には実際の患者さんを追ったドキュメンタリーが放送されました〔注2〕。
意識ははっきりしていて目や耳は働いているけれども身体が動かない。呼吸筋が動かなくなる時点で、人工呼吸器を付けるか、付けずに死を受け入れるか の選択を迫られる。観念的に見れば、人の命とは何かということを考えさせられる非常に象徴的な病気なんですが、患者さん本人やご家族にとってはそんな抽象 的な話ではないわけで……。
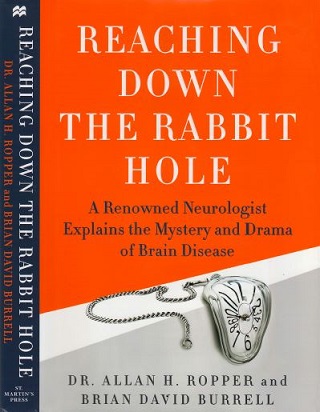
米国ボストンの病院の脳神経科病棟の日々をドラマチックに描き出すReaching Down the Rabbit Hole。Dr. Allan Ropperが神経内科医で、Brian Burrellが共著のライターです。(邦訳は河出書房新社より刊行予定)
実は、今翻訳している本の中にALSの話が出てきます。ボストンのティーチング・ホスピタル(医師育成の役割を担う病院)の脳神経科病棟を舞台にし たノンフィクションで、ALSだけではなく、神経の病気が疑われるさまざまな患者が次々と病院にやってきます。懐かしのテレビドラマ「ER」のような緊迫 した場面があるかと思えば、NHKの「ドクターG」のような原因究明の謎解きもあり、一気に読まされる、そして訳していて楽しい本です。でも、ALSの章 は気楽には訳せません。
人工呼吸器を選択した患者、拒否した患者、そしてその家族。それぞれの思いと、微妙に揺れる医師の気持ち。三浦春馬さんのドラマも事実を踏まえて丁 寧に作られていたと思いますが、この本や、実際の患者さんを追ったドキュメンタリー番組にはやはり、善し悪しを超えたノンフィクションならではの説得力が あります。
ノンフィクション作品は事実の翻訳
しかし、ノンフィクションが事実のすべてを伝えているとはかぎりません。というよりも、病気の現実のすべてを伝えることなどできるはずもありませ ん。ドキュメンタリー番組の患者さんは、自身のお別れ会を企画して笑顔で亡くなっていきましたが、たしかにそれは真実の一面ではあるのでしょうけれど、そ れだけではなかったはず。ノンフィクションとはいえ、必ず書き手、作り手のフィルターを通して、その意図を反映した側面が描き出されるものです。
そういうところは、翻訳者の仕事と似ていますね。訳文のすべてを原文と同等(equivalent)にすることなどできはしない。直接的な意味を取るか効果を取るか、いずれかの面を選び、どこかの面を捨てなければならない。そこには翻訳者としての意図が働きます。
ノンフィクション作品がそのように作られているとしたら、いったいフィクションとの違いは何なのでしょう。
実際、今訳している本も、ある有名な脳神経科(神経内科)医〔注3〕の 1人称の語りというスタイルなのですが、実際には別のライターが書いていると思われます。表紙に脳神経科医と並んでライターの名前が出ているので、ゴース トライターではなく、共著という形ですが。ライターが一から書いているわけではないでしょうが、少なくともリライトはしているはず。そのような形は、言っ てみれば「言語内翻訳」なのかもしれません。表紙に原著者と並んで名前を載せているという点で、私たちと同じです。
ノンフィンション作品は事実を翻訳している。そう考えてみたらどうでしょう。
ノンフィクションライターは、事実のある側面を取り上げて光を当てる。私たちも、原文のある側面を強調し、ある側面を消すことができます。
しかしそれは、好きなようにしていいというものではありません。原著者の意図を尊重する姿勢を失ったら、もはや翻訳ではありません。翻訳には翻訳自体の意図があるとしても、翻訳の意図が原著者の思いを踏みにじるようなものであったなら、それこそ裏切り者です〔注4〕。ノンフィクション作品も、書き手の切り取り方次第とはいえ、少なくとも事実をありのままに伝えようという姿勢があってこそのノンフィクションなのだと思います。
線引きはけっして単純なものではないと思います。ALSのドキュメンタリー番組では、延命拒否の判断の理由として介護のたいへんさ――自分の延命が 介護をする親の命を縮めてしまう――が強調されていました。今訳している本でも、家族の負担を思う患者の気持ちが描かれています。自分の立場で想像してみ ても、それは真実に違いありません。けれども、あまり強調されていない「金銭的な問題」も大きいはずなんです。真実を伝えるために何を選択するか。このあ たりは、きっと制作者にとっても難しい判断だったに違いありません。
誠実さという資質
事実を踏まえながらも、そこに作者が投影した側面を強く描き出すタイプの歴史小説があります。私は、江戸時代の架空の人物が事件を解決していくよう な「時代」小説は好きなんですが、いわゆる「歴史」小説というのがどうも苦手で、自分でもなぜだろうと疑問に思っていたのですが、先日ある歴史物のドラマ を見ているときに気づきました。歴史小説は小説であるかぎりフィクションなのに、どうしてもノンフィクション的に受け取ろうとするために、まるで「勝手 訳」〔注5〕を読んでいるような気分になってしまうのです。
これは私の受け取り方が悪いので、歴史ドラマも、フィクションとして見れば何の問題もないはず。でも、ついそう感じてしまうというのは、翻訳家とし て染みついた「原著者に(事実に)忠実であろうとする気持ち」ゆえなのかもしれません。オリジナルに対する2次的な解釈のあり方に、ひどく敏感なのです。 歴史的事実の記述であっても、それは厳密に言えば解釈でしかありえないのですが、どうせ解釈だと開き直っているか、それでもなんとか真実を見失うまいと足 掻いているか、その違いが気になります。
これはけっこう翻訳の肝になる部分かもしれません。翻訳者には、言語能力も調査能力も必要ですし、推理力、総合的判断力など、多くの力が求められま す。しかし、実はいちばん大切な資質は、「誠実さ」とでもいうものではないかと思うのです。「忠実」とはちょっと違う「誠実さ」。それなしには、翻訳な ど、錨の切れた船のように、どこへでも漂ってしまいます。しょせん裏切り者であることを自覚しつつの誠実さですから、けっして単純な美徳ではないのですけ れども。
さて、今回をもって私のコラムはいったん終了となります。ご愛読いただいた皆様、ありがとうございました。またどこかでお目にかかれましたら幸いです。
(初出 サン・フレア アカデミー e翻訳スクエア 2015年1月26日)
